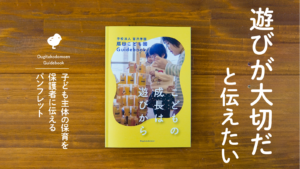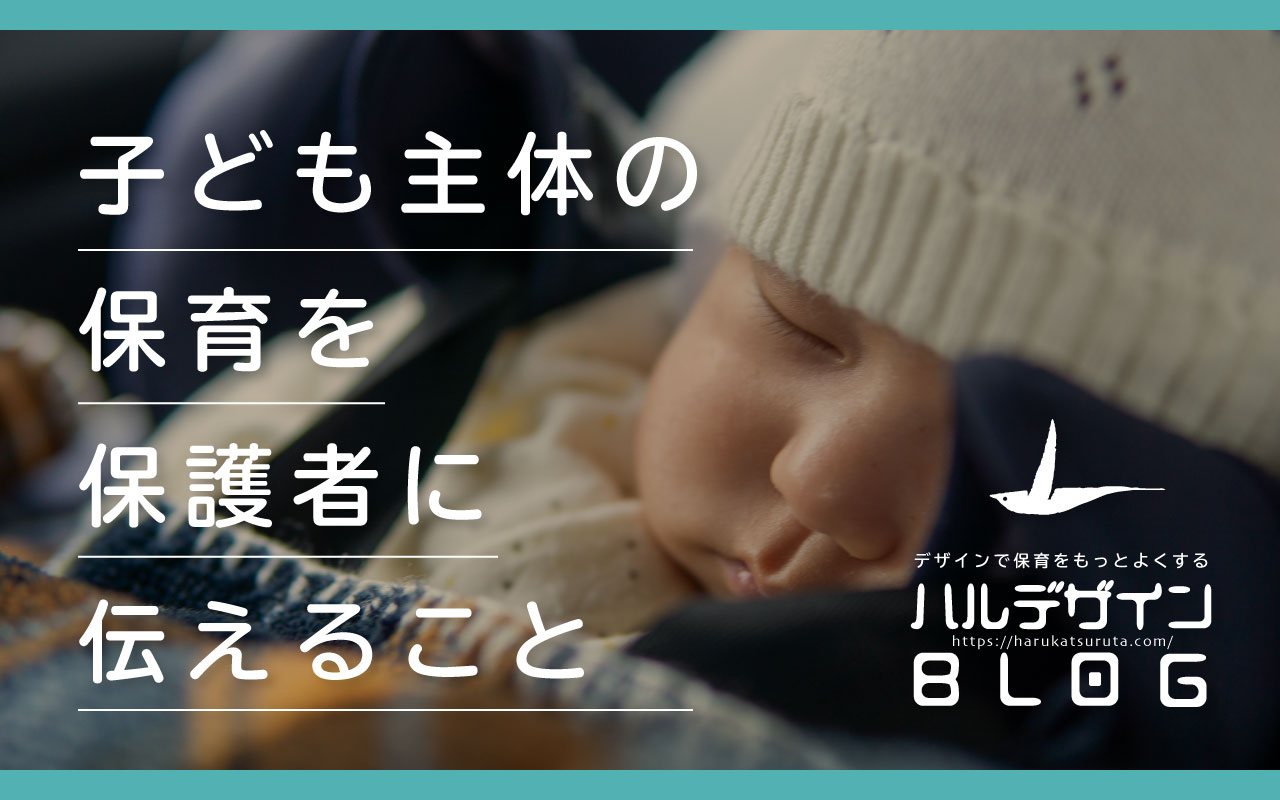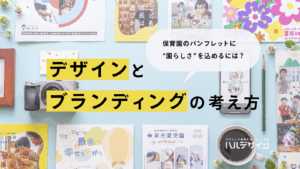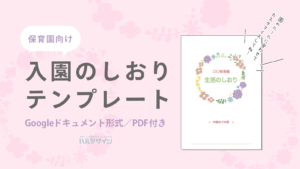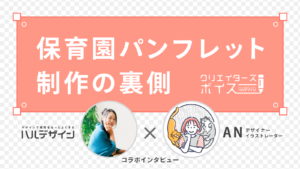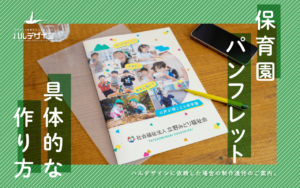こんにちは「デザインで保育をもっとよくする」ハルデザインです。
今回は、
保育園、こども園で園長先生や主任先生、研修の担当をしている先生方向けに
子ども主体の保育を保護者に伝えることについて書きたいと思います。
このブログの内容は保育施設でパンフレットを作成する際に職員会議でお話させてもらった内容を編集したものです。
なぜ子ども主体の保育を保護者に伝えるのか
保育施設は小中学校など学校と違って、
施設ごとに全部ちがいます。
小学校なら基本的に先生が教室の前に立って子どもたちは自分の席について授業を受けますよね。
保育施設の場合、
例えば、
先生が前に立ってクラスみんなで同じ活動をすることもあれば、自由に子どもたちが好きな遊びをしていることもあります。
大抵の保育施設にはその両方の時間がありますが、その割合が園によってかなりちがいます。
ほとんど設定活動をしている園もあれば、
ほとんど自由遊びをしている園もあります。
(他にも多くの違いがあります)
アプローチは違うけれど、どこの保育施設も子どもの幸せを願っているところは同じですね。
ただ、これまで保育施設は待機児童がたくさんいて、保護者が選べない状況がありました。
保育施設の方針に納得して入園できればいいですが、納得できなかったら、保護者にとっても、子どもにとっても、園にとっても不幸ですよね。
多様なアプローチがあるのはとってもいいことだと思うので、
保護者が園を選べるようになるといいなと思います。
子ども主体の保育を保護者に伝える3つのポイント
私は仕事で保育施設のパンフレットを作っているのですが、
実は従来、保育施設のパンフレットといえば、理念、デイリー、年間行事、活動など…を載せるものだったのです。
もし、自由保育を重視している。遊びの中で子どもが育つということを大切に考えている園ならば、遊びが大切だということを保護者の人に伝えた方がいいと思うんですよね。
しかし、これが難しい…。
遊びの中で子どもが育つと言っても、保育の専門家ではない保護者にとっては、とても分かりにくい話です。
ただ子どもが好き勝手に遊んでるだけだと思う人もいるでしょう。
そんな子ども主体の保育を保護者に伝えるポイントが3つあると考えました。
- 写真と短い文章で伝える
- エピソードで伝える
- 子どもの成長を伝える
ドキュメンテーションのこと
子ども主体の保育を伝える方法を模索していたところ、
保育ドキュメンテーションというものを知りました。
ドキュメンテーション聞いたことある方いますか?
保育ドキュメンテーションとは、
写真付きのエピソード記録
だそうです。
元々、イタリアのレッジョ・エミリアという町で生まれた記録様式のことらしいです。
(「レッジョ・エミリア」は幼児教育でとても有名。)
保育の記録についての2つの考え
保育の記録はみなさんどこの園でも作られていることと思います。
書き物が多くて大変…ですよね。。
保育の記録は書かないといけないから書いている・・・ということになりがちですね。
ここには2つの考えがあって、
1つ目は記録を作る手間を無くす。
最近はICT導入の追い風もあって、保育施設用の業務支援システムがたくさんでてきています。
定型のテキストを選んで記録を作るシステムを使っている園があったり、
(まだ実用化されたかわからないのですが、)
保育の中で保育者の発言を音声認識で読み取ってAIが記録をつけるシステムが開発されていたりするみたいですよ。
自動で記録を作ってしまおうという話です。
園によっては記録をつけるために残業が発生しているらしく、
保育者の記録を作成する作業負担が課題になっているようです。
しかし、なぜ、保育の記録をとっているのでしょうか?
保育の振り返りのために記録をとっているのですよね。
次に活かすために、
保育者の成長のために、
保育の質を上げるために
記録をしているのですよね。
そう考えると、記録が簡単にできたり、自動でできたりするのは振り返りの意味はなくなってしまいます。
自動で記録ができると例えば排泄とか朝の体調とか、
チェックポイントが決まっているようなことについては
長い期間で定点観測的なデータが蓄積するという意味はあるとは思いますが。
しかし、振り返りとしての記録にはなりませんね。
そこで、
2つ目、保育の質向上につながるように記録をとる
そのためにドキュメンテーションのような記録法があると思います。
事実だけの記録ではなく、感じたこと気づいたことを記録することで、
自身の振り返りになり、
共有すれば他の人の視点や気付きを知ることができますね。
ドキュメンテーションの目的は保育の質を高めることだそうです。
- 自身の保育の振り返り
- 同僚と共有して同僚との対話
- 子どもと共有すれば子どもとの対話
- 保護者と共有すれば保護者との対話
のツールとして活用できます。
今後
園でドキュメンテーションに取り組み保育を振り返っていく中で、
園の大切にしている保育が写真とエピソードで形になってくると思いました。
それぞれの園が大切にしている保育を保護者の方にも伝えていけるように私も考えていきたいと思います。
参考にした本
「日本版保育ドキュメンテーションのすすめ」
ドキュメンテーションをする目的から、
いつ作るとか手書きの場合やパソコンの場合など具体的な作成方法、
どのように活用するなど方法論、
実際にドキュメンテーションに取り組んでいる園の事例の紹介など、
1冊読めばドキュメンテーションを始めることができる内容です。
私は保育者ではないので、写真を撮影する目的は違いますけど、こんな話していたら、私も写真を撮りたくなってきました。
こちらの記事も読みませんか?